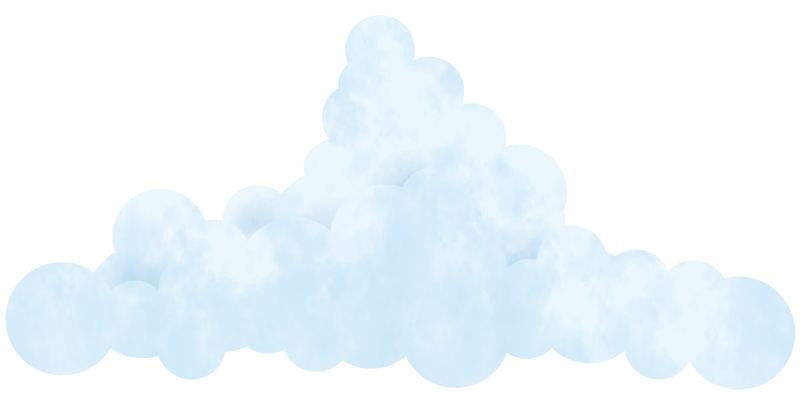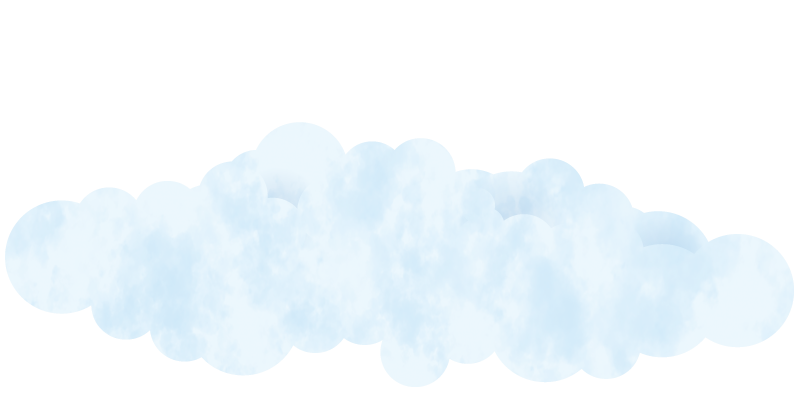こう水をふせぐ努力
人々のどのような努力によって、蒼社川は安全な川になったのだろう。
流れを変える工事は、たいへんむずかしいものでした。しかし安固はひるまず、自らも先に立って働き、13年もの年月をかけて、蒼社川の工事は完成しました。
安固が行った工事のおかげで、こう水はへり、田畑が広がり、周辺の村の人々を助けました。
今治藩では、工事が終わったあとも「※宗門堀」とよばれる方法で、「川ざらえ」を毎年行い、こう水をふせぐ努力を続けました。
※宗門堀
宗門堀とは、宗門帳(今の戸籍簿)に記された15才から60才までの男子全員行う川ざらえのことで、上流から流れ出た土や砂をほりあげて、ていぼうをがんじょうにする工事のこと。藩のとの様も自ら工事の指揮をとりました。初めは周辺の農民のみでしたが、後に町人にもぎむを負わせ、藩全体で工事に取り組みました。
むかしの作業で使われた道具
 じゃかこ
じゃかこ
石を中に入れ、川にしずめ、川岸がくずれるのをふせぐ かけや
かけや
くいを打ちこむための道具 土つき
土つき
土を上からたたいておさえしっかりさせる道具 もっこ
もっこ
石や土を入れて運ぶ道具 くわ
くわ
土をほりおこすための道具
 広がる水田(玉川)
広がる水田(玉川) 実法寺に残る安固の墓
実法寺に残る安固の墓
 川の流れをつけかえるために、たくさんの人々のたいへんな努力があったんだね。
川の流れをつけかえるために、たくさんの人々のたいへんな努力があったんだね。
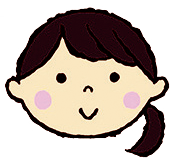 そのおかげで、蒼社川の周辺の田畑は、たくさんの作物を実らせるようになったんだよ。
そのおかげで、蒼社川の周辺の田畑は、たくさんの作物を実らせるようになったんだよ。
安固は川を治めるために、さまざまな工事を行い、人々のためにつくしました。その働きをみとめられ、約をしりぞいてからも、との様の相談役となりました。安固の墓は、鳥生に、今も残っています。